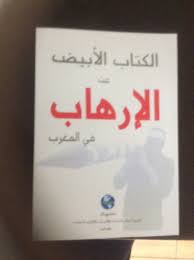
『モロッコテロリズム白書』は、モロッコのテロリズムを、その萌芽期から厳座に至るまでの理解の試みにおいて、初めての資料的価値をもつ文献のひとつである。同書は分析を重視したアプローチで、国内のテロ活動と地域・国際的な地政学的環境との相互の関係性を検証している。
同書は、日本のITEAS(国際トランスリージョナル・エマージングエリア研究グループ)による出版。同書では国際法と国際関係の研究で広く認識されている定義に基づいてテロリズムを定義している。このアプローチは、イスラームのイメージを持った宗教的言説で殺人をカモフラージュし、欧米とアラブ・イスラーム世界の文明間の緊張を高めて実行されるテロリズムを理解するために必要である。
同書では、テロ集団がメンバーを「情熱的な」テロ実行者に仕立てるために用いる、さまざまな教化や意識・感情操作の分析に重点がおかれている。テロ集団による教化や操作によって、生きる権利や共存という価値を否定し、「他の」ジェンダーや人種・宗教を排除する政治的プロジェクトを擁護するようになる。
モロッコの事例に戻ると、同書の特徴の一つに、テロリズムという現象は2003年5月16日のカサブランカのテロ攻撃から始まったのではなく、それ以前から始まったものであるという理解に基づいた分析を具体的におこなっている点がある。モロッコでのテロは、自分たちのイデオロギーに反対する人々に対する暴力的攻撃を肯定する過激派集団シャビーバ・イスラミーヤの、内部的なダイナミズムのなかから生まれていることが、資料的裏付けをもって分析されている。
モロッコの左翼指導者が暗殺された事件が、「説法協会」のような組織の解体につながったが、しかし同時に「断片化されたサークル」と同書の著者が呼ぶものを生んでしまった。「モロッコのムジャヒディーン運動」「モロッコ・イスラミック戦闘者集団」「イスラムの選択」といった集団は、多くの「細胞」を持っていた「シャビーバ・イスラミーヤ」から派生したものであった。
また、同書は増大するテロの脅威に対する外からの影響も無視していない。アフガニスタンやボスニア、イラクでの戦闘に参加したモロッコ人らが、国内のテロの脅威を増大させる上で果たした役割が丹念に分析されている。
アル・カーイダのビン・ラディンがスーダンを離れ、アフガニスタンに移るという決断の後に、アル・カーイダが活動の拠点とした「崩壊国家」や、「IS(イラクとシリアのイスラム国)」についても分析されている。
さらに、サヘル、シリア、イラク、パキスタン・アフガニスタン地域といった紛争地帯での戦闘に、数百人、数千人単位のモロッコ人がいるという事実は、非常に大きな警告であると指摘している。彼らは戦闘の中で得たノウハウを、自国に戻った時に使おうと考える。彼らの多くが(国内ではなく)遠く離れた場所で戦闘に参加しようと決意したことは、モロッコの予防的・先行的政策の成果であるといえる。解体された「細胞」はどれも、アルジェリアの経験に着想を得て、山岳地帯や農村地帯に軍事訓練キャンプを設営しようという目標を持っていたことがわかっている。
同書は、モロッコのテロ対策戦略の有効性は、その先見性と多面性にあると結論づけている。モロッコのカウンターテロリズムの諸政策のなかで最も重要な要素は、治安面での徹底した対策が、宗教的空間の再構築と組み合わされている点である。さらにそれが、脆弱性や周縁化という社会的疎外を撲滅するために人間を中央に見据えたアプローチを土台にしている点にある。
2000年以来、130以上のテロ細胞が解体され、研究者にとっては豊かなデータがもたらされた。それによって事実に基づいた分析が可能となった。これまで2003年5月16日の自爆テロの実行犯の大半は、貧しい家庭で生まれ育ったものであるとされ、テロリズムと貧困の関係が指摘されていた。しかし、同テロ事件にかかわった者のリストを精査すると、彼らの多くは安定した階層、なかには裕福な階層に属していたことが判明し、これまでの「投影的なアプローチ」について、同書は否定的にみている。
さらに、テロに関連して有罪となった者の大半は、「悪の予防」という考えに基づいて「暴力的な懲罰」を行ったと考えている。したがって、倫理的な「良心の咎め」が、組織的な暴力を正当化することにつながる、本来の教義からは外れた破滅的な考え方への入り口となっていることがしばしばである。
テロリストに至る道は、多くの場合、組織のなかで少しずつ「育まれて」いく。少しずつ知的・政治的プロジェクトが醸成しされていくのである。したがって、テロ行為の「知的基盤」と過激思想との関係について議論を深めていく必要性が、同書では指摘されている。またテロに対する闘いにおいて、地域間協力が不十分であることも指摘されている。
同書では、サヘルの状況、特にマリでのサーバル作戦の結果が、同地域でのテロや組織犯罪、近隣諸国でのテロのリスクとの関連で分析されている。また分離運動のポリサリオ戦線のメンバーの中に、「イスラーム・マグリブ地方のアル・カーイダ」やMUJAO(西アフリカ統一聖戦運動)の考えに傾倒するものがいることが示され、ホスト国の責任に関しても指摘されている。さらに国家責任に関する国際法の原則から、テロの地域的・グローバルな局面はテロを理解する上で重要であり、実際、それは多くの国におけるテロ対策に貢献するモロッコの治安当局の諸策の分析から読み取れることが指摘されている。
『モロッコテロリズム白書』は、テロリストのやり方がどう機能しているか、視聴覚メディアやインターネットを使った教化の方法、個人が他者を傷つけるために自己破壊をすることを受け入れるよう準備・訓練する方法についても明らかにし、分析している。また、同書にはサレ裁判所で扱われたすべてのテロ事件の年譜がつけられており、礼拝所、国や国家主権にとって象徴的な場、公的人物、観光・経済のインフラ、欧米の権益、特にアメリカの権益を狙って、国を不安定化させるという恐ろしい計画を明らかにしている。この資料に基づいた年譜は、それ自体で、テロが拡大していったこの15年間に関心を持つすべての研究者にとって価値を持っている。
結論として、同書は、テロの脅威のグローバル化に直面する現在、真の国際協力が治安面だけではなく、さまざまなレベルで必要とされていることを明らかにしている。それは、あらゆる国と共同体を脅かすテロに関する正確なデータと穏当な分析によって示されている。国際協力は、モロッコがこれまでおこなってきたテロとの闘いに加えて必要不可欠なものである。
以上の理由から、同書は、テロ対策に関する研究書としてこれまでの類書に見られなかった多くの新たな知見を有している。ITEASはこれをより多くの専門家の利用が可能となるよう、アラビア語、英語、スペイン語、フランス語、日本語で出版する予定である。これらの言語による出版は、テロ対策の最も重要なステップの一つである研究者間の知識の共有や共通の戦略の構築、国家間の情報の交換を促進すると考えられる。
